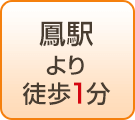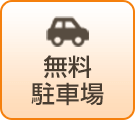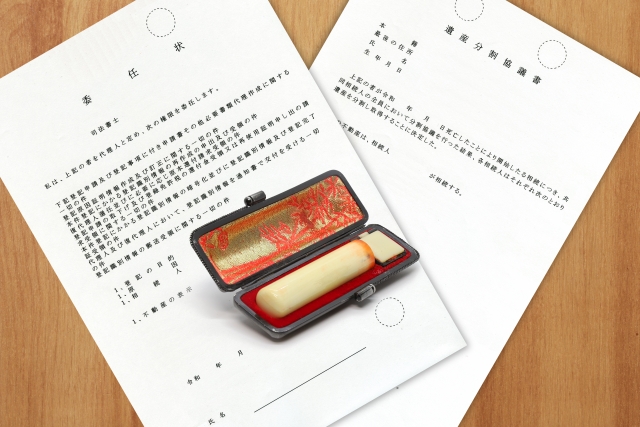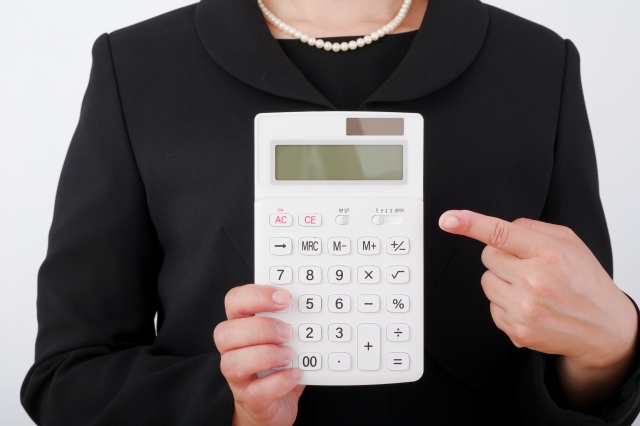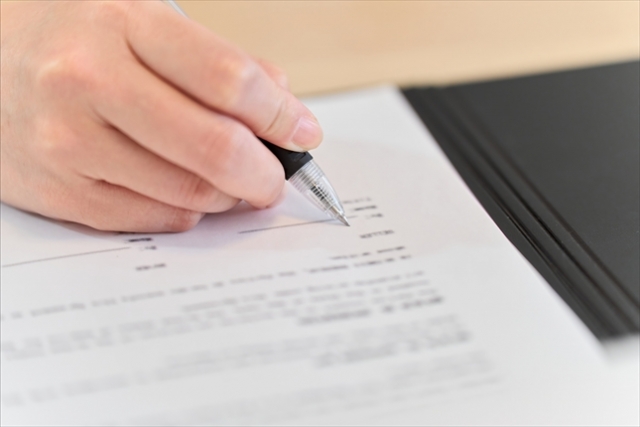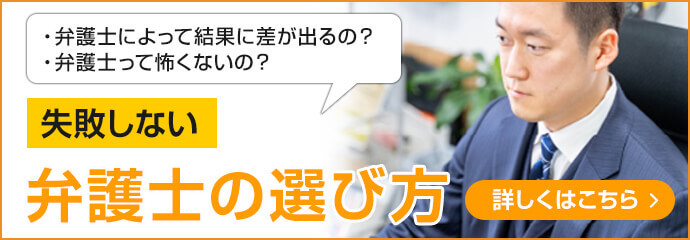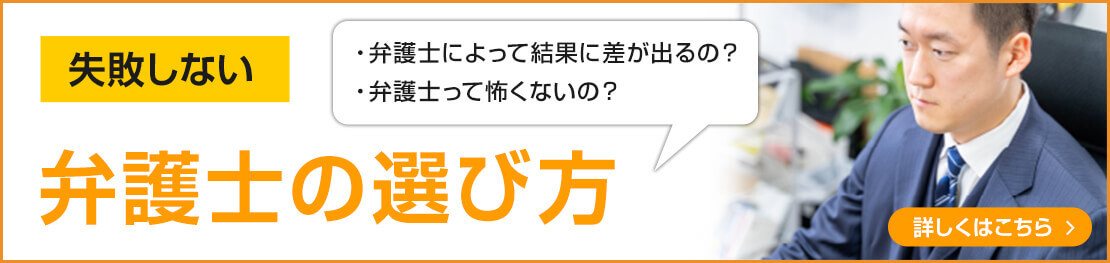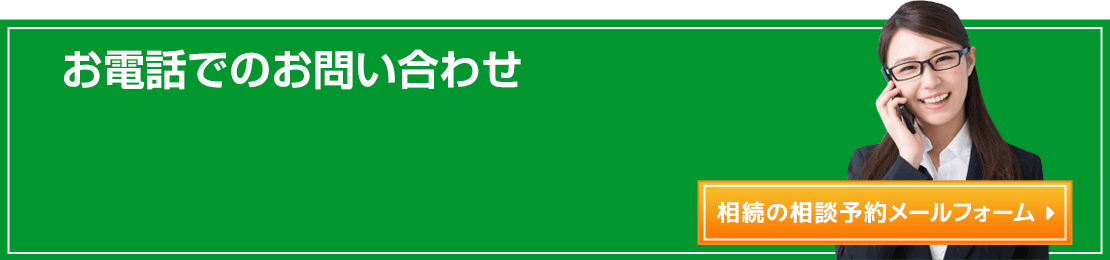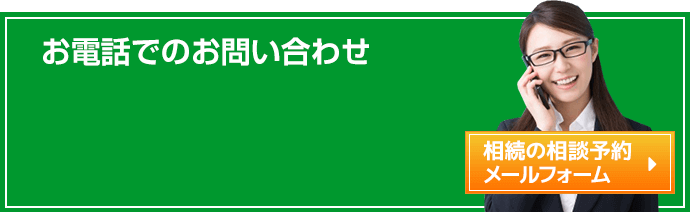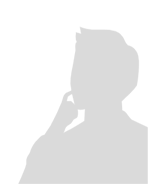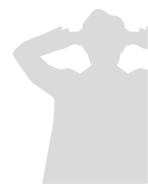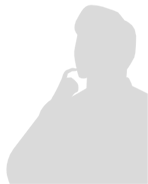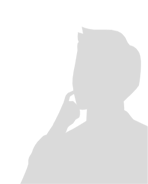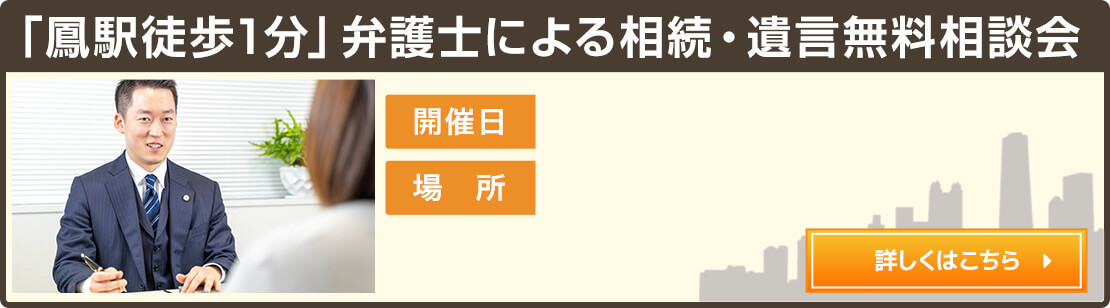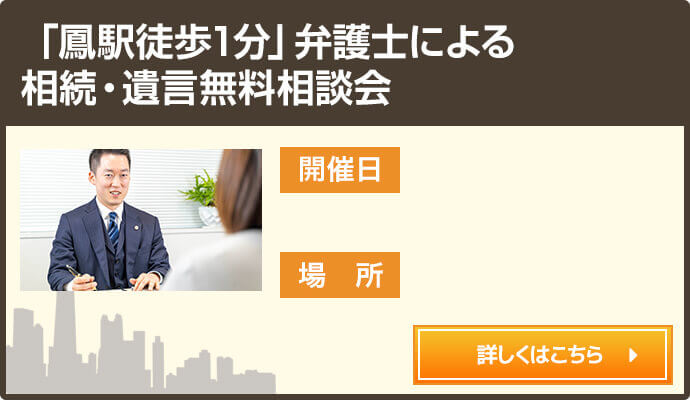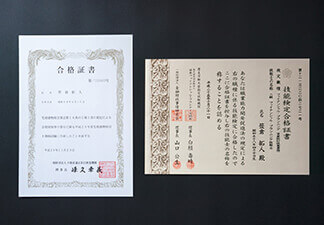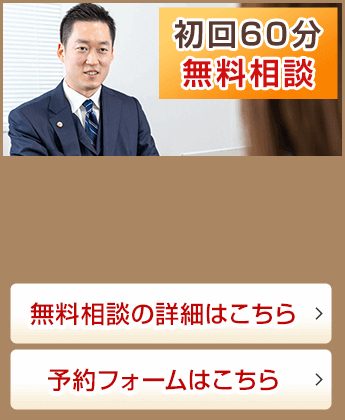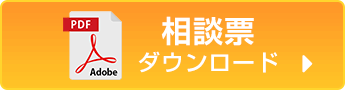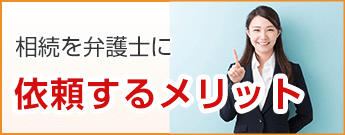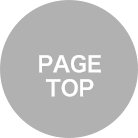Q&A - Page 2
-
【Q&A】遺言書はどうやって保管すればよいですか?
-
自筆証書遺言は自宅内で机の引き出しやタンスの中、銀行の貸金庫などに保管する方が多いですが、法務局や弁護士に預けるのもお勧めです。公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。 1.遺言書を保管するときの注意点 遺言書は、 […]
-
相続税の手続きは、何からスタートすればよいのか?
-
まずは基礎控除額を算出し、相続税申告の要否を確認しましょう。そのためには、相続人と相続財産の調査を行う必要があります。 1.基礎控除額とは 基礎控除額とは、相続税を計算する際に差し引かれる非課税枠のことであり、次の計算式 […]
-
相続した共有不動産を売却する場合の注意点
-
相続した共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。ただし、共有持ち分だけなら自由に売却できます。 1.共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要 遺産の中に不動産が含まれている場合、遺言書がなく、遺産 […]
-
【Q&A】遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったらどうすれば良いですか?
-
原則として、遺言書の内容に従って遺産を分割することになります。ただし、相続人全員で新たに合意すれば、遺産分割協議の内容に従って遺産を分割することも可能です。 1.原則として遺言書が優先される 遺言書は被相続人の最終意思が […]
-
【Q&A】相続税の基礎控除はどうやって計算する?
-
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。ただし、法定相続人の数え方や、相続税の申告の要否などについて、いくつかの注意点があります。 1.相続税の基礎控除とは 相続税の基礎控除とは、 […]
-
【Q&A】相続税の申告期限はいつまでですか?
-
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に、相続税の納付までを済ませる必要があります。 1.相続税の申告期限 相続税の申告期限は、多くの場合、被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日 […]
-
【Q&A】公正証書遺言はいつまで保管されるのですか?
-
公正証書遺言の原本は、公証役場で一般的に140~170年間にわたって保管されます。ただし、保管期限内でも公正証書遺言が無効となるケースもあることに注意が必要です。 1.公正証書遺言の保管期限 公正証書の保管期限は公証人法 […]
-
不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続はどうなる?相続手続きの注意点や相続税を解説
-
不動産を共有している方が亡くなると、その方の持ち分は相続の対象となります。そのため、もう片方の共有名義人が、亡くなった方の持ち分を優先的に取得できるわけではありません。 亡くなった方の相続人とのトラブルを回避するためには […]
-
【Q&A】遺産分割協議が終わった後に新たな財産が見つかったらどうすれば良いですか?
-
基本的には、新たに見つかった財産の分割方法を決めるだけで良いですが、高価な財産が見つかった場合などでは、遺産分割協議のやり直しが必要となることもあります。 1.遺産分割協議のやり直しは原則不要 新たな財産が見つかったとし […]
-
【Q&A】相続した土地について売却したいが、どのような相続手続きを経るのか?
-
まずは相続人の中で誰が土地を相続するのかを決め、相続登記を行った上で、不動産会社へ売却を依頼することになります。売却と並行して相続税の申告・納付や、売却後に譲渡所得税の確定申告が必要となる可能性があることにも注意が必要で […]