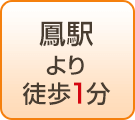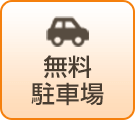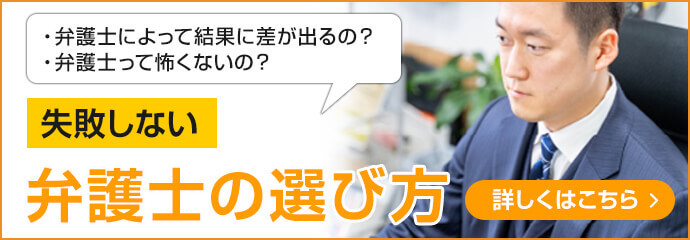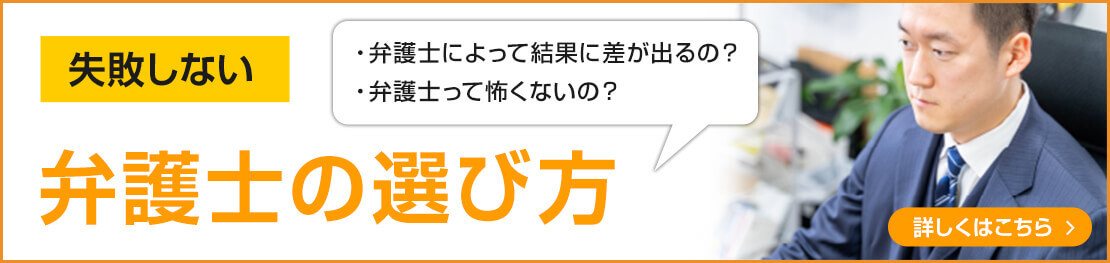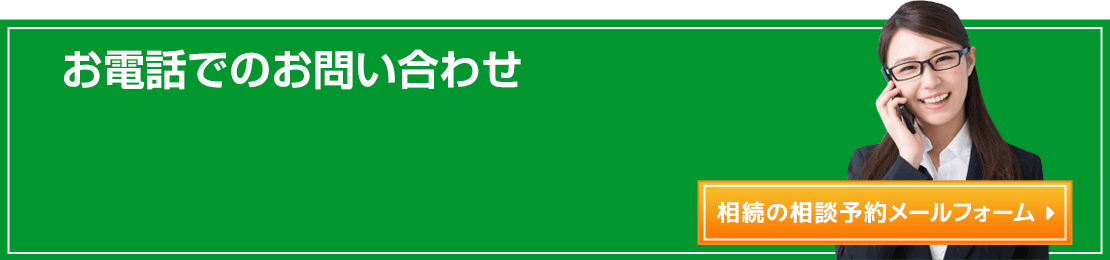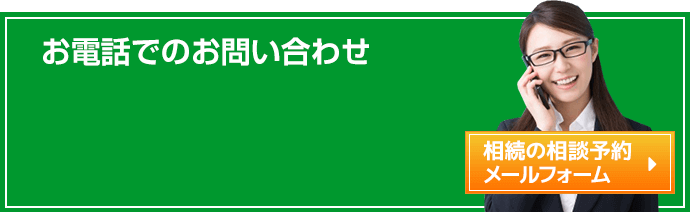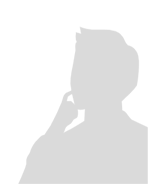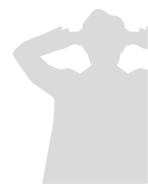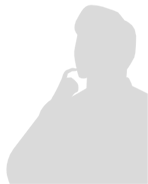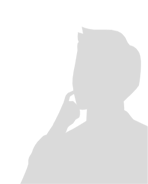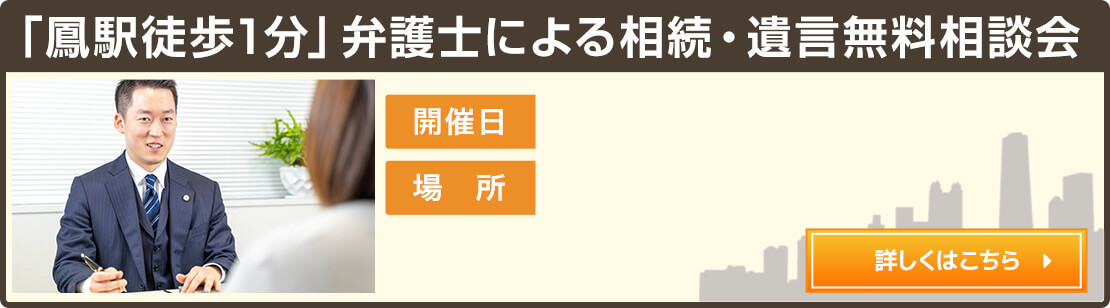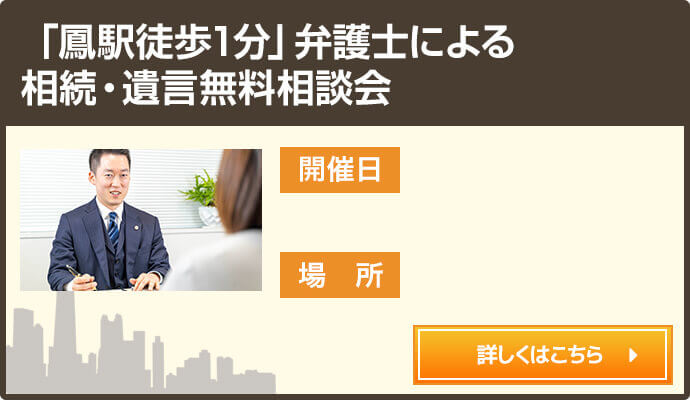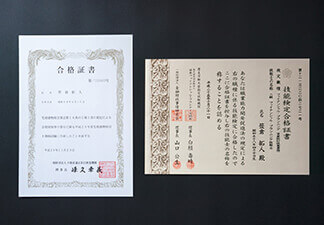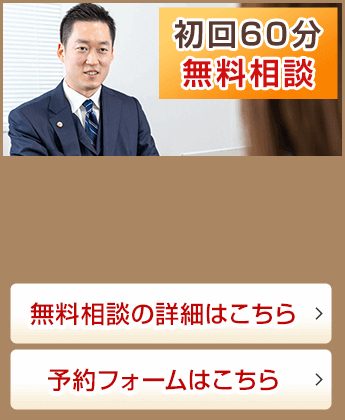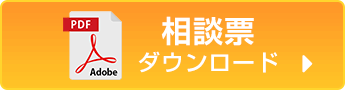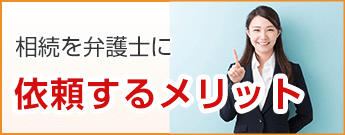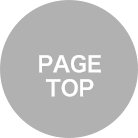遺言の作成がなぜ必要なのか?相続に詳しい弁護士が解説
目次
遺言の作成は、ご自身が亡くなった後の遺産分割を円滑に進めるために有効かつ重要なものです。
とはいえ、「うちは家族や親戚の仲が良いから」、「大きな資産もないから」などの理由で、遺言作成の必要はないと考えている方も多いことでしょう。
しかし、実際のところ、遺言を作成していれば防げたのに、遺言がないことで相続トラブルに発展してしまうことが多々あるのが実情です。
そこで今回は、遺言の作成が必要な理由についてわかりやすく解説します。
1.遺言が無い場合のリスク
遺言とは、被相続人の生前における最終意思を、残された人たちに表示するためのものです。被相続人が誰にどの財産を渡したいのかを決めていたとしても、遺言書を作成していなければ、その意思は死後に反映されません。
遺産の分け方は相続人たちに委ねようと考える方も多いですが、ご自身の死後、相続人間でトラブルが発生する可能性があることには注意が必要です。
遺言がない場合には、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。それまでは仲の良かった家族・親戚であっても、「少しでも多くの遺産を受け取りたい」「思い入れのある遺産を自分のものにしたい」「自分が親の面倒を見ていたのに他の相続人と同じ額なのは納得できない」などの思惑が交錯し、トラブルに発展するケースは多々あります。
このように、遺言がなければ思わぬ相続トラブルを招くリスクがあるということを知っておきましょう。
2.今すぐに遺言の作成を検討すべきケース
あらゆるケースで遺言が必要とまではいえませんが、以下のケースでは、今すぐに遺言の作成を検討することをおすすめします。
特定の相続人に多く財産を渡したい
遺言を作成することにより、誰が、どの財産を、どれだけ取得するのかを指定することができます。したがって、特定の相続人に多くの財産を渡すことが可能となります。
遺言がなければ遺産分割協議が行われますが、相続人間で意見が対立する場合には、基本的に法定相続分が尊重されます。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分のことです。例えば、配偶者と長男、二男が相続人となる場合には、配偶者の相続分が1/2、長男と二男の相続分が1/4ずつと定められています。
このケースで、例えば妻に法定相続分よりも多くの財産を渡したい場合は、遺言を作成することによって、その意思を実現させることが可能です。
特定の相続人に財産を渡したくない
逆に、特定の相続人に財産を渡したくないという意思も、遺言の作成によって実現させることができます。
例えば、上記のケースで二男に財産を渡したくないという場合は、妻と長男に財産を相続させ、二男には何も相続させないという内容の遺言を作成することが可能です。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の相続分が保障されていることにもご注意ください。上記のケースでは、二男の遺留分は遺産総額の1/8となります。相続トラブルを回避するためには、遺留分にも配慮した内容の遺言を作成した方がよいでしょう。
なお、遺言によって特定の相続人を廃除できる可能性もあります。相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった相続人の相続権を剥奪する制度のことです。家庭裁判所の審判を経る必要がありますが、廃除が認められた場合、その相続人は、遺留分を請求する権利も失います。
上記のケースで、二男が廃除の要件に該当すると考えられる場合は、遺言で廃除の意思を示しておくとよいでしょう。
相続人がいない、あるいは複雑である
相続人がいない場合や、相続関係が複雑な場合も、遺言によって誰にどの財産を渡すのかを指定しておくことが有効です。
遺言を作成すれば、相続人以外の人に財産を渡すことも認められます。相続人がいない方は、お世話になった人などに財産を渡す内容の遺言を作成しておくとよいでしょう。内縁の配偶者などにも、遺言を作成することで財産を渡すことが可能となります。
相続関係が複雑なケースの代表例としては、前妻との間に子がいるケースや、認知した婚外子がいるケースなどが挙げられます。
前妻との間の子や認知した婚外子も相続人となりますが、これらの相続人に財産を渡したくない場合は、他の相続人へすべての財産を渡す内容の遺言を作成するとよいでしょう。
ただし、これらの「子」にも遺留分がありますので、その点に配慮した内容を検討することも大切です。
分割しにくい財産がある
遺産の中に不動産や非上場株式のように、分割しにくい財産があるときの相続についても、遺言を作成しておくことが有効です。
一般的に不動産の価値は高額ですが、預貯金のように物理的に分割することは難しいため、その分け方をめぐって相続人同士でもめやすい傾向にあります。
非上場株式についても、時価の評価方法が複雑である上に、誰も取得を望まないことも多く、遺産分割でトラブルの元になるケースが少なくありません。
このように分割しにくい財産がある場合には、遺言でその分け方を指定しておくとよいでしょう。
3.遺言の種類と選び方
遺言には、次の3種類があります。
|
種類 |
特徴 |
|
自筆証書遺言 |
遺言者本人が本文を手書きし、署名・押印して作成する遺言 |
|
公正証書遺言 |
公証人が遺言者から遺言内容を聴き取って作成する遺言 |
|
秘密証書遺言
|
遺言者本人が作成した遺言書を入れた封筒を封印し、その存在のみを公証人が証明する遺言 |
自筆証書遺言は手軽に、かつ、費用をかけずに作成できますが、要式の不備や不明確な記載などによって無効になりやすいというデメリットがあります。自分で保管することになるため、紛失や破棄、改ざんなどのおそれがあることにも注意が必要です。
公正証書遺言なら無効になりにくく、紛失や破棄、改ざんなどのおそれもありません。しかし、公証役場での手続きに労力と費用がかかるというデメリットがあります。
秘密証書遺言には、ご自身が亡くなるまで遺言内容を誰にも知られないというメリットがありますが、自筆証書遺言と同様に遺言が無効になりやすいことと、公証役場での手続きに労力や費用がかかるというデメリットがあるため、実務上はあまり利用されていません。
法的に有効な遺言を作成し、残された人へ確実に意思を伝えるためには、公正証書遺言を選ぶのは望ましい選択肢の一つです。
また、自筆証書遺言でも、弁護士に作成を依頼すれば無効となることを回避できます。完成した遺言書は弁護士の事務所で預かってもらえることもありますし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。
したがって、弁護士に依頼する場合は、自筆証書遺言も有力な選択肢となるでしょう。
4.遺言に関して弁護士に相談するメリット
遺言を作成するなら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
相談するだけでも、遺産分割トラブルの回避につながる遺言内容の決め方や、遺言書の書き方などについて、具体的なアドバイスが受けられます。
また、弁護士に遺言の作成を依頼することもできます。どの種類の遺言を作成する場合でも、弁護士が全面的にサポートしてくれるので、法的に有効で、内容的にも適切な遺言の作成が可能となります。
さらに、弁護士には遺言の執行も依頼できます。遺言の執行とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことです。
遺言の中で弁護士を遺言執行者に指定しておけば、ご自身の亡き後は弁護士が遺言執行者として、確実に遺言の内容を実現してくれます。
5.当事務所の特徴とサポート内容
遺言に関するお悩みは、ぜひ堺鳳法律事務所へご相談ください。
当事務所では遺産相続の分野を積極的に手がけており、年間100件以上は遺産相続に関するご相談に対応しております。
遺言書作成の実績も豊富にあり、専門的な知識とノウハウを蓄えておりますので、お客様の状況に合わせて臨機応変に対応し、最適なご提案を差し上げることが可能です。
また、当事務所の代表弁護士は不動産や相続税に明るく、税理士や宅建士、AFPの資格も有しております。遺産の中に不動産がある事案や、財産関係が複雑な事案、相続税対策が必要な事案でも、適切に対応することができます。
相続に関するご相談は初回60分まで無料です。土日や夜間も、ご予約いただければ相談可能です。ご事情によりご来所が困難な方のために、入院先等まで出張させていただくことも可能です。
遺言に関する問題は、早めにご相談いただくことが大切です。遺言の作成が必要かどうかについてのご相談だけでも構いませんので、気になる方はお気軽に当事務所へご相談ください。