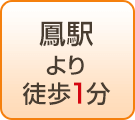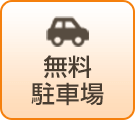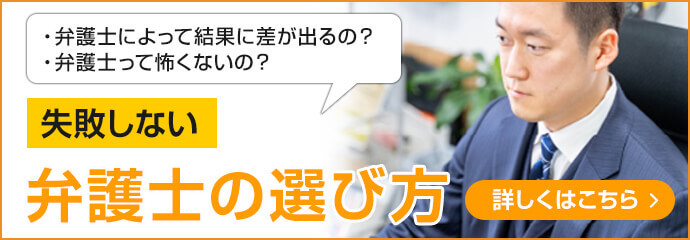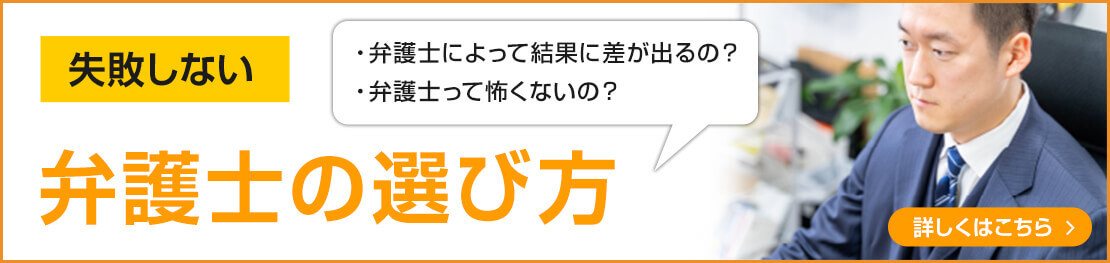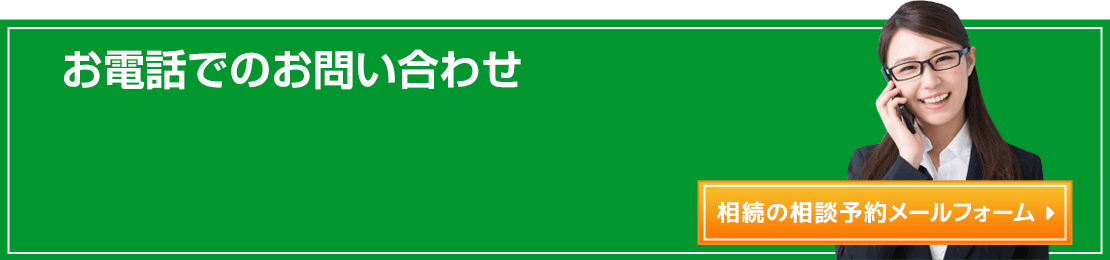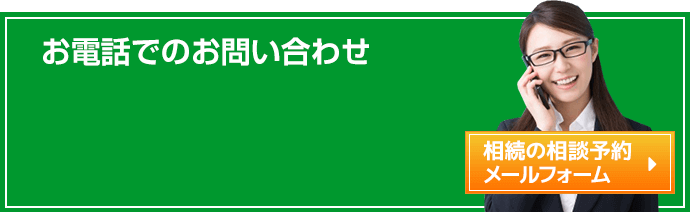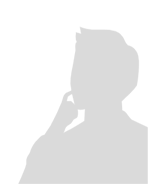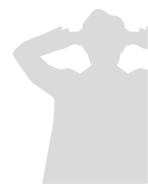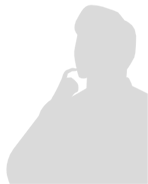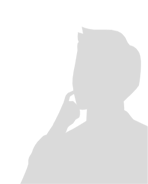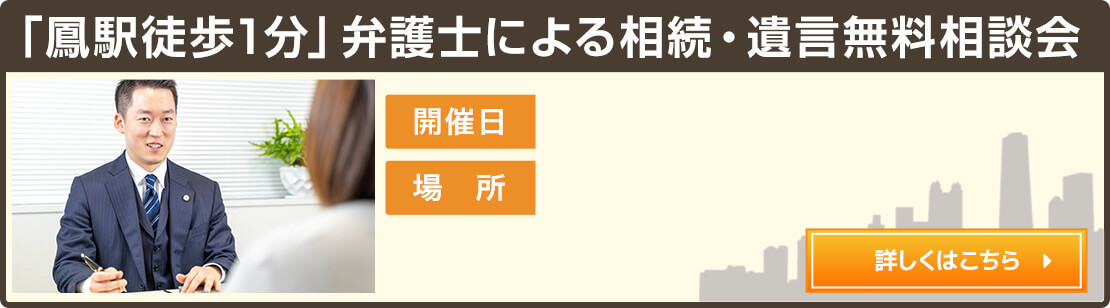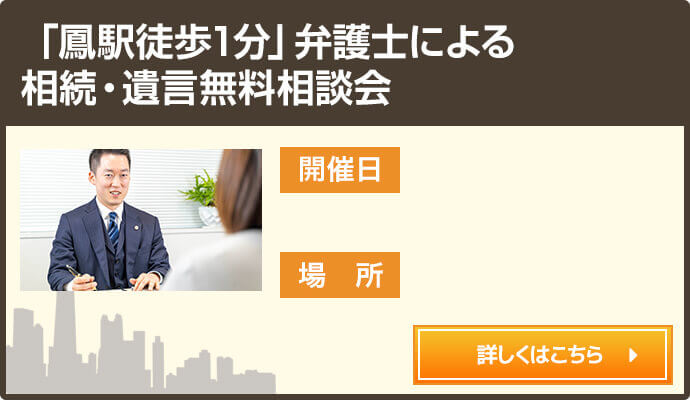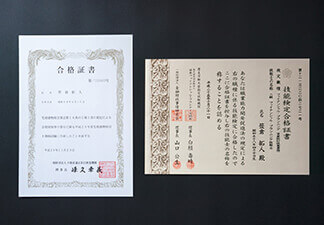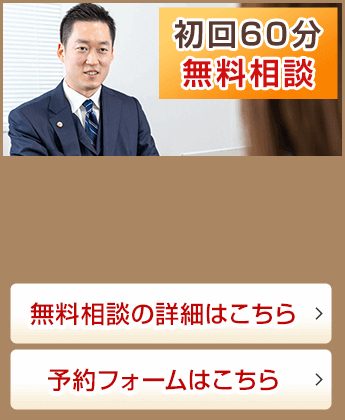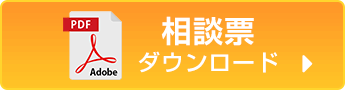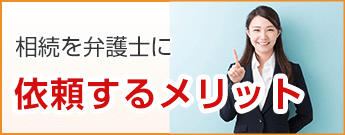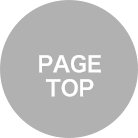【Q&A】遺留分を計算する際の「財産」には何が含まれますか?
- 2025.10.03

遺留分を計算する際の「財産」には、相続開始時に被相続人が有していた財産と、生前に贈与された財産が含まれます。ここから債務額を控除した額が、「財産」額となります。
1.遺留分を計算する際の「財産」に含まれるもの
遺留分を計算する際の「財産」に含まれるものは、以下のとおりです。
(1)相続開始時の財産
被相続人が亡くなった時点で有していた預貯金や不動産などプラスの財産は、遺贈されたものも含めて、遺留分の計算対象に含まれます。
なお、生前に不正に出金された預貯金等がある場合、被相続人が不当利得返還請求権を有していたものとして、財産額に加えることが可能な場合があります。
(2)生前贈与された財産
生前贈与された財産については、基本的に、相続開始前の1年以内に贈与されたものに限り、遺留分の計算対象に含まれます。
ただし、相続人に対して生前贈与された財産のうち、特別受益に該当するものについては、相続開始前の10年以内に贈与されたものが、遺留分の計算対象に含まれます。
なお、贈与の当事者双方が遺留分を侵害することを知って贈与を行った財産については、期間の制限なく遺留分の計算対象に含まれます。
2.財産額から控除されるもの(債務)
被相続人が、借金やローン、病院や介護施設への未払金などの債務を抱えていた場合は、その合計額が、財産額から控除されます。
3.遺留分の計算対象とならない財産
遺留分の計算対象とならない財産としては、以下のものが挙げられます。
・祭祀財産
・生命保険金
・相続開始前1年より前に贈与されたもの(相続人に対する贈与で特別受益に該当するものについては、相続開始前10年より前に贈与されたもの)
祭祀財産とは、仏壇、位牌、墓石、墓地など先祖を祀るための財産のことであり、そもそも相続の対象外です。
生命保険金も原則として相続の対象外ですが、保険金の額が遺産に対して著しく高額である場合は、特別受益に準じるものとして、遺留分の計算対象に含まれることがあります。
4.遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、次の計算式によって算出します。
遺留分侵害額=遺留分算定の基礎となる財産の価額×遺留分割合×請求権者の法定相続分
「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は、「相続開始時の財産+生前贈与された財産-債務」です。
遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の1/3、その他の場合は法定相続分の1/2です。
遺留分の計算は意外に複雑なケースが多いので、正確に計算するためには弁護士に相談してみることをおすすめします。