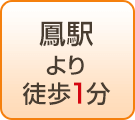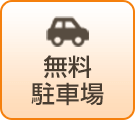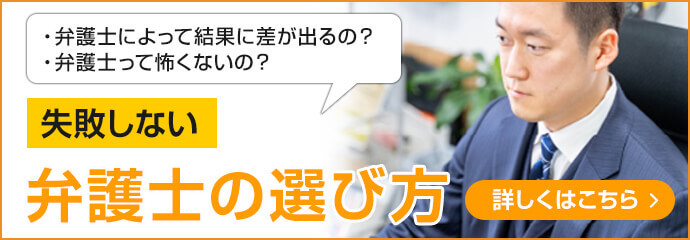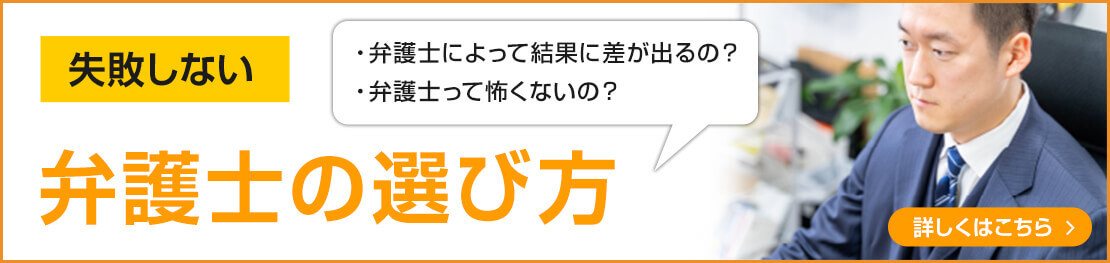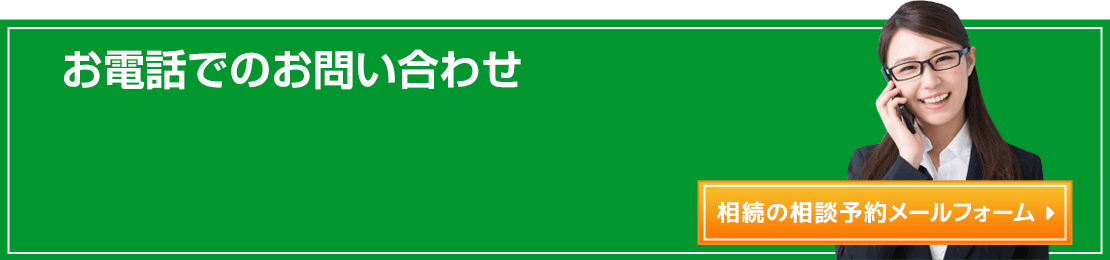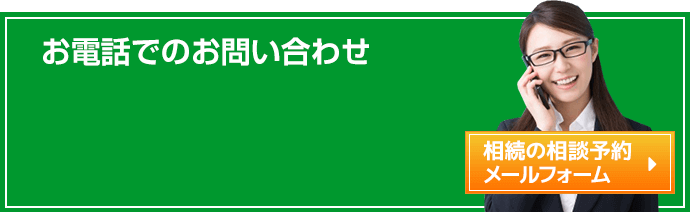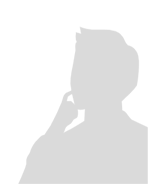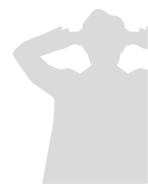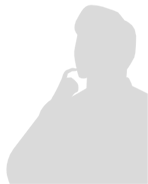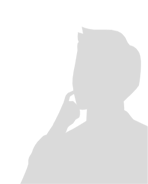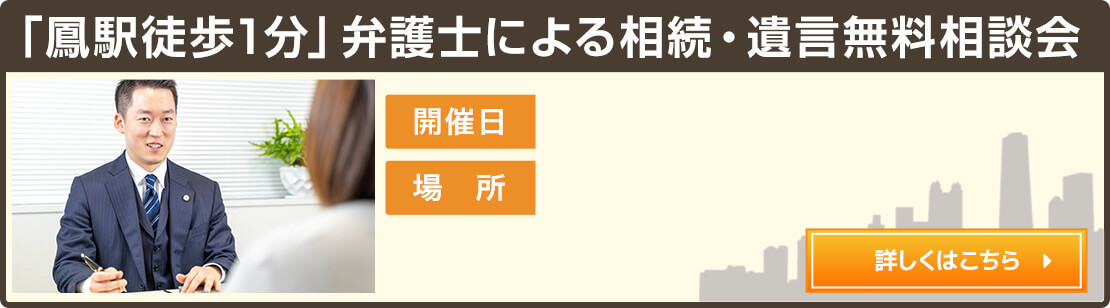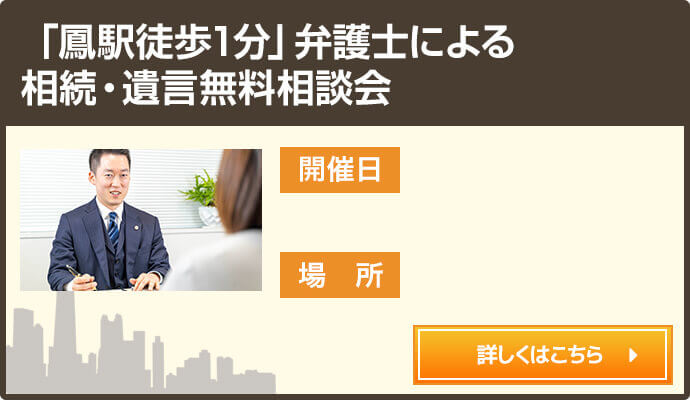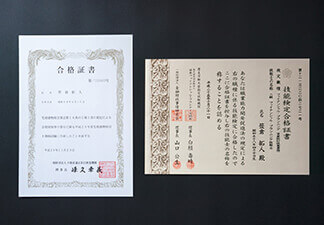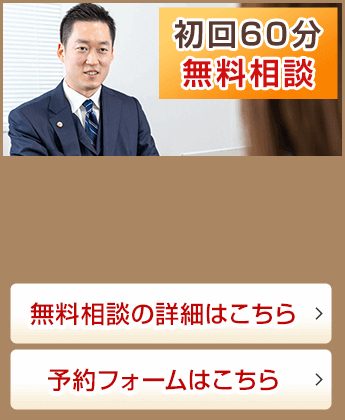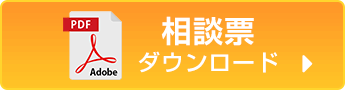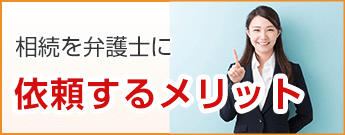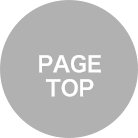【Q&A】どのような場合に遺言が無効となってしまうのでしょうか?
- 2025.06.15

遺言の方式に不備がある場合や、内容が不明確な場合、認知症の方が遺言書を作成した場合などで、遺言が無効となることが多いです。
1.遺言が無効となるケース
遺言書が無効となるのは、以下のようなケースです。
(1)方式に不備がある
遺言は、民法で定められた方式に従って行わなければ無効となります。
特に自筆証書遺言では、以下のような方式の不備により無効となることが多いので、注意しましょう。
・本文が手書きされていない
・日付が記載されていない、または日付を特定できない
・署名や押印がない
・訂正の仕方が間違っている
(2)内容が不明確である
方式に不備がなくても、内容が不明確な遺言は無効です。
例えば、預金が複数あるのに、「預金は妻と子に相続させます」と書かれていた場合は、どの預金を誰が取得するのかが不明確なため、無効となるでしょう。
預金を特定の相続人に相続させる場合は、金融機関名等によってどの預金を指すのか明確にし、それを誰に相続させるのかまで記載する必要があります。
(3)内容が公序良俗違反に違反する
不倫相手にすべての財産を譲るといった遺言は、公序良俗違反として無効となる可能性があります。
ただし、公序良俗違反に該当するかどうかは、具体的な事情に応じて判断されます。
(4)遺言能力がない状態で作成された
遺言者が認知症などで、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力を欠く状態で作成された遺言書は無効です。
ただし、認知症の程度は様々ですので、認知症の診断を受けている人のすべてが遺言能力を欠くわけではありません。
認知症の程度や、遺言内容の複雑さなどの事情を総合的に考慮して、遺言の有効性が判断されます。
(5)詐欺、脅迫、錯誤などにより作成された
誰かに騙されたり、脅されたり、あるいは勘違いによって遺言が行われた場合には、取り消せる可能性があります。取り消された場合には、その遺言の効力はなくなります。
(6)偽造や変造(改ざん)された
第三者が遺言者になりすまして作成したり(偽造)、内容を改ざんしたり(変造)した遺言書は、遺言者本人が作成したものではないため、無効です。
(7)連名で作成された
遺言書を連名で作成することはできません。夫婦であっても、連名で作成した遺言書は無効となります。
(8)複数の遺言書がある
複数の遺言書が見つかった場合は、内容が矛盾する部分については、最新のものだけが有効となり、古いものは無効となります。
これに対して、内容が矛盾しない場合は、どちらも有効となり得ます。例えば、1通目は不動産について、2通目は預金について書かれているような場合です。
2.遺言書の作成は弁護士への依頼がお勧め
遺言書を作成する際には、細かなルールをすべて守らなければなりません。
遺言の無効を回避するためには、弁護士に依頼して遺言書を作成することをお勧めします。