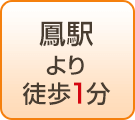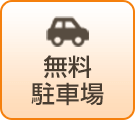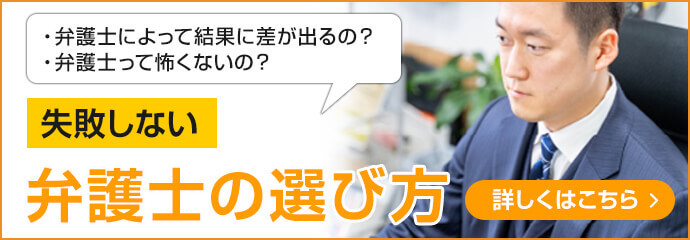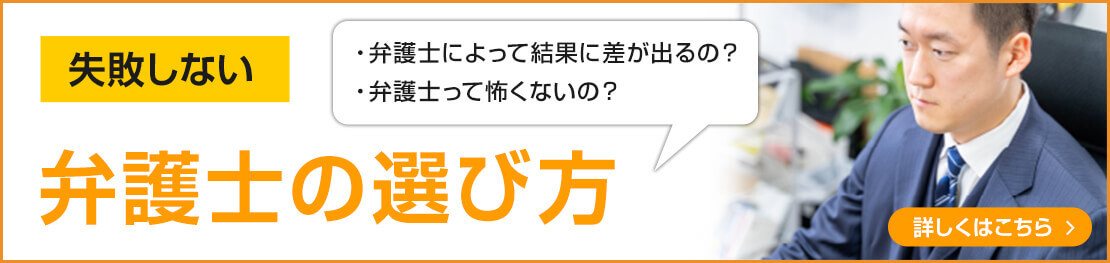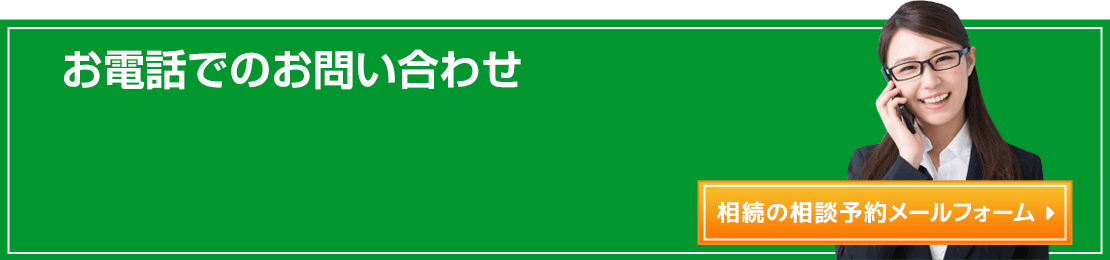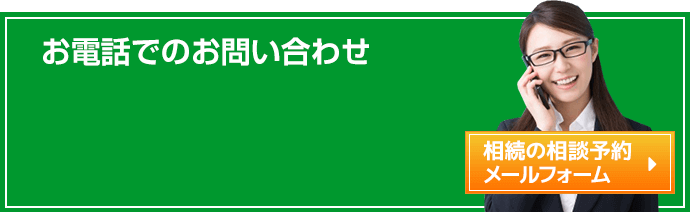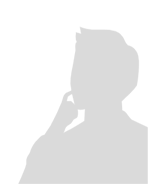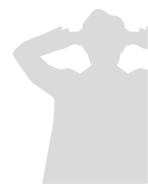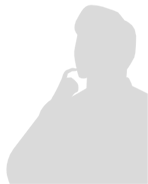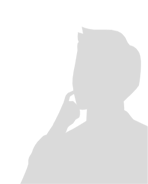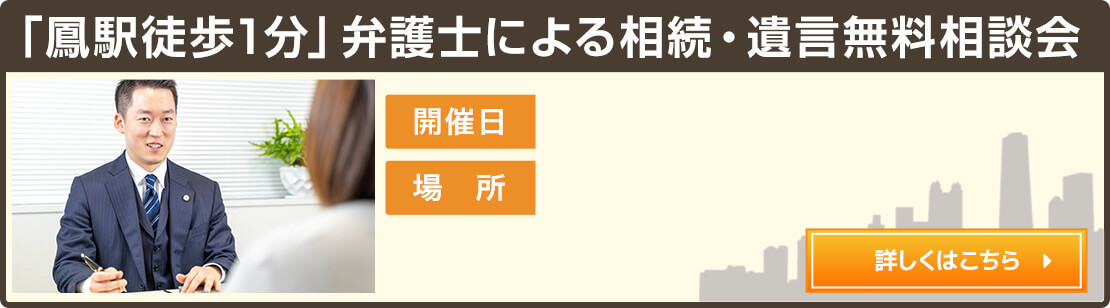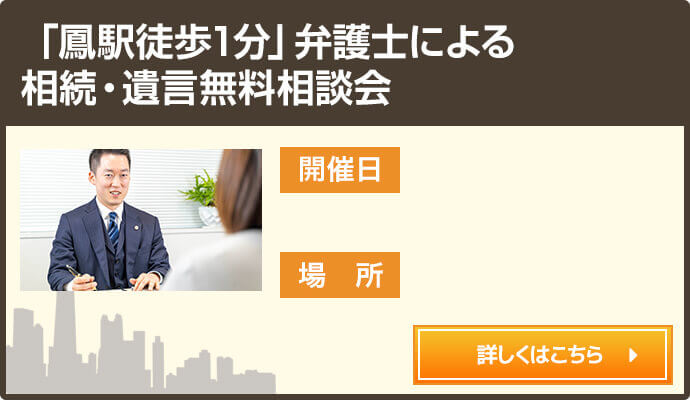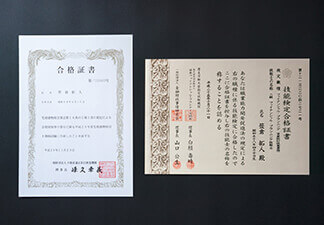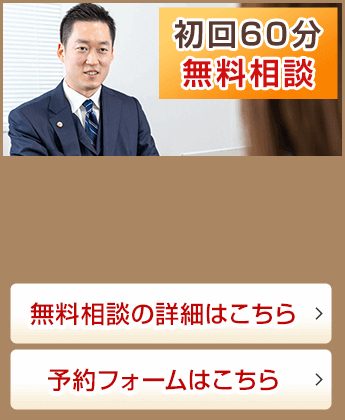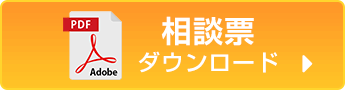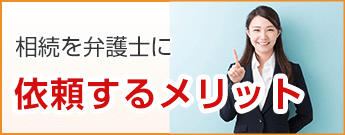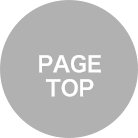相続した共有不動産を売却する場合の注意点
- 2025.05.16

相続した共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。ただし、共有持ち分だけなら自由に売却できます。
1.共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要
遺産の中に不動産が含まれている場合、遺言書がなく、遺産分割協議(調停や審判を含む)も行わなければ、その不動産は相続人全員の共有となります。
また、遺産分割協議が成立して、相続人の1人が不動産の権利をすべて取得することとなったとしても、もともと2名以上の共有名義だった不動産の持ち分を相続したため、相続人以外の人と共有になってしまうこともあります。
共有名義の不動産を売却するためには、法律上、共有者全員の同意が必要とされています。そのため、共有者の中に1人でも「売りたくない」という人がいる場合には、その人を説得して同意してもらわなければ、その不動産を売却することはできません。
2.共有持ち分のみを売却した場合のリスク
不動産全体ではなく、共有持ち分のみを売却する場合には、他の共有者の同意は不要です。したがって、自分の共有持ち分のみを第三者に売却することによって、共有関係から脱退することはできます。
ただし、共有持ち分のみでは利用価値が乏しいことから、売却価格は評価額よりも大幅に安くなりやすいことに注意が必要です。
また、自分ではなく他の共有者が共有持ち分を売却した場合には、買主がその不動産に出入りしたり、使用したりするのを拒むことはできません。買主がその不動産を使用しない場合でも、共有持ち分に応じた賃料の支払いを請求される可能性があります。
3.不動産の共有を解消する方法
このように、不動産が共有名義のままでは、売却が難しくなることも多いです。そのため、不動産を売却する可能性がある場合は、なるべく単独名義にしておいた方がよいでしょう。
遺産分割協議が終わっていない場合は、なるべく単独名義になるよう、遺産分割協議を進めたほうが良いでしょう。
遺産分割協議が終わったものの共有名義とした場合や、相続開始前から相続人以外の人と共有名義だった場合は、そ
共有名義で相続してしまったの不動産を単独名義に変更するためには、自分の共有持ち分を他の共有者に買い取ってもらうか、他の共有者の共有持ち分を自分が買い取ることになるでしょう。しかし、その場合にも買い取り価格をめぐって共有者間でもめてしまう可能性があります。
また、他の共有者の共有持ち分を買い取りたいものの、話し合いがつかない場合は、共有物分割請求訴訟を提起して、判決によって、一定の金銭の支払いと引き換えに、他の共有者の共有持ち分を取得できる場合もありますが、必ずしもそのような判決を得られるとは限らないため、このような場合は弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。
共有持ち分を無償で譲る場合には、贈与に該当するため、贈与税がかかる可能性が高いことにも注意が必要です。
4.不動産の相続は、なるべく単独名義で
最初から単独名義で不動産を相続すれば、相続後に売却しやすくなりますし、買い取り価格や贈与税をめぐるトラブルも回避できます。
そのためには、遺言書の作成や生前贈与なども含めて、遺産分割のトラブルを回避するための方策が重要となります。
最善の方策を見つけるためにも、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、不動産が含まれるご相続について豊富な取扱実績を有しており、遺言書の作成や生前贈与などの生前対策から、遺産分割協議の対応等について的確に対応することが可能です。
また、共有名義となっている不動産の処理について揉めてしまったような場合でも、遺産分割協議や共有物分割訴訟等によって解決した実績があります。
共有不動産の売却についてお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。