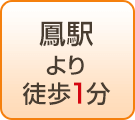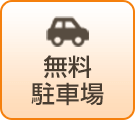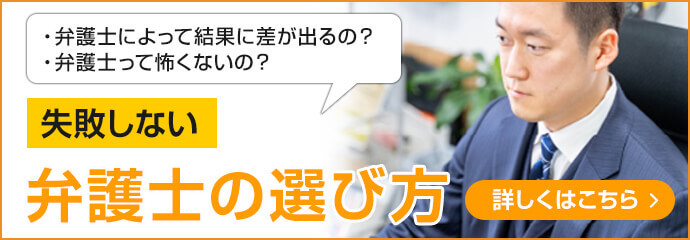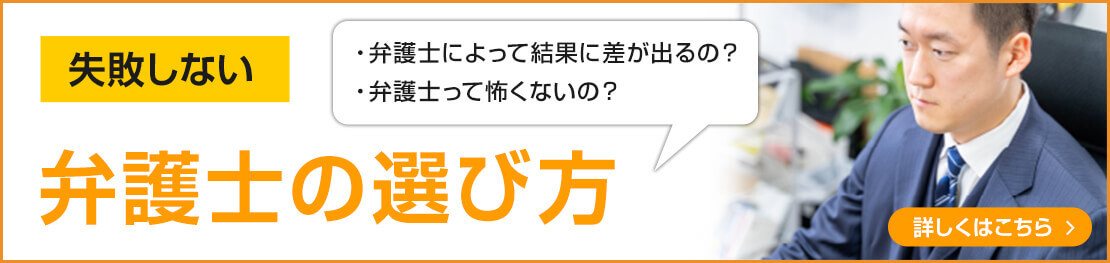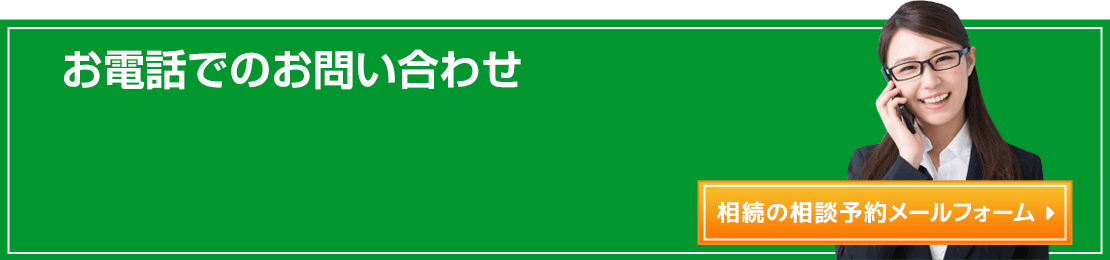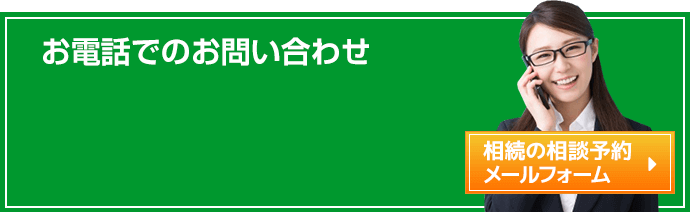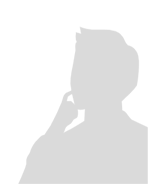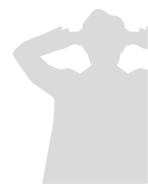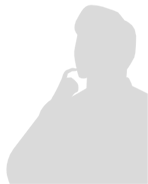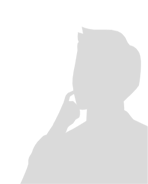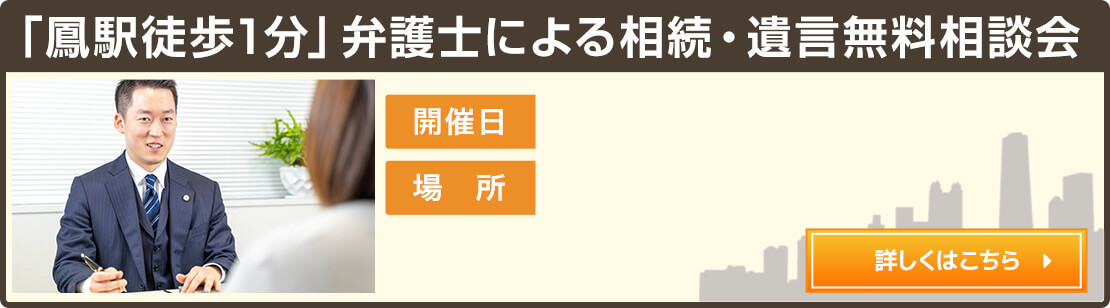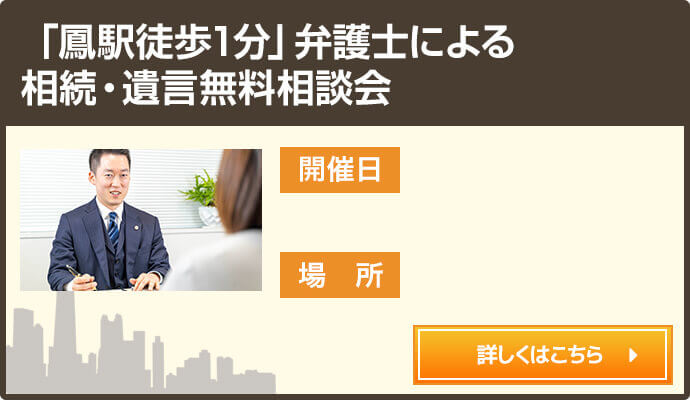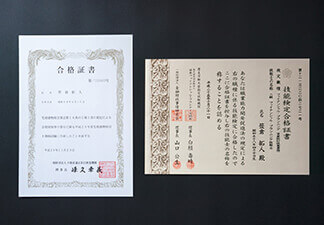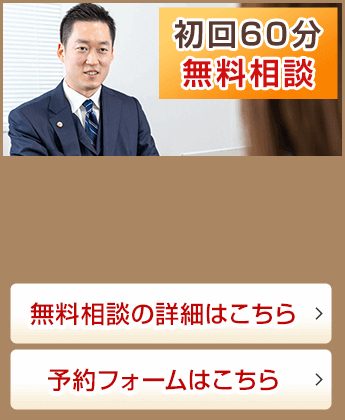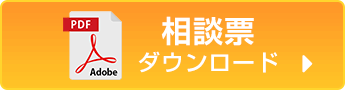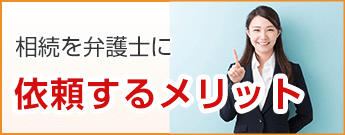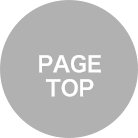親と同居していた兄弟が遺産を使い込んでいたらどうする?相続に詳しい弁護士が解説
目次
遺産は残された相続人の間で公平に分けるべきものですが、一部の相続人が勝手に遺産を使い込むことも少なくありません。
今回は、親と同居していた兄弟が遺産を使い込んでいた場合に、公平な遺産分割を実現するためにやるべきことや注意点、使い込みを未然に防止する方法などについて解説します。
よくある財産の使い込み事例
当事務所では、弁護士への相続のご相談で、特に多くあるのが
- 兄弟から遺産の目録が届いたけど、思っていたよりもやけに預貯金が少ない…
- 親の預貯金が生前に同居している兄弟に使い込まれていた。
- 兄弟が親を囲い込んでおり、親の財産を使い込んでいる可能性がある。
というご相談です。
親の介護をしていた、もしくは親と一緒に住んでいた兄弟が、無断で親の預貯金の引き出しを行い、これを自分のために使い込んでいたことが発覚したというのが典型です。
実際に、当事務所では、亡くなられた方名義の口座の明細を銀行等から取り寄せて、生前の預貯金の動きを確認したところ、数百万円から数千万円に及ぶ多額の出金がなされていたことが判明する例をよく見かけます。その他にも、亡き親名義の不動産や株式、車などを無断で売却したり、貸しアパート・マンションの賃料を着服したりして、そのお金を使い込んでいるケースも少なくありません。
財産の使い込みが発覚した場合に相続人が取るべき行動
相続開始前に親以外の者によって預金が引き出された場合、それが親の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は、引き出しを行った人に対して、その返還を求めることができます。
しかし、相手方がスムーズに返還に応じるとは限りません。そのため、以下の流れで行動を進めていくことが重要です。
通帳・取引履歴の確認
まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いつ、いくらの預貯金が、どこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。
通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。
もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、大変有益な資料となります。
相手方に説明を求める
預貯金が引き出されていたとしても、兄弟が使い込んだものとは限りません。親の介護や看護、その他の必要経費に使った可能性もあります。そこで、相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。
必要経費に使ったのであれば、その旨の説明があるはずです。合理的な説明がない場合や、説明を拒否した場合などは、私用で使い込んだ可能性が高いと考えられるでしょう。
必要経費に使った旨の説明があった場合でも、証拠が何もなければ嘘を付いている可能性があることに注意が必要です。
請求額を算出し支払いを求める
相手方が遺産を使い込んだ疑いが濃厚な場合は、使い込んだ金額の支払いを求めることになります。
使い込んだ金額を正確に算出するのは難しいこともありますが、基本的には、使い途について合理的な説明のない「使途不明金」について全額(請求する側の相続分に応じた額)、支払いを求めるべきです。
もっとも、相手方に支払い能力がなければ、現実的に全額は取り戻せないこともあります。使い込まれた金額にもよりますが、相手方の支払い可能な範囲内の金額で和解することも検討するとよいでしょう。
いずれにせよ、当事者同士での話し合いでは双方が感情的になってしまうことも多いです。感情的に対立してしまうと話し合いを進めることも難しくなりますので、冷静に話し合えない場合には、弁護士を通じて交渉することをお勧めします。
話し合いで合意ができたら、和解書を作成します。分割払いになる場合は、支払いが途中で滞る可能性もあるため、和解書を公正証書にしておいた方がよいでしょう。
訴訟を提起する
話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いを拒否する場合には、訴訟を提起して法的に解決を図る必要があります。
どの裁判所に訴訟を起こすのかというと、原則的には「地方裁判所」で行います。
なお、家庭裁判所における遺産分割調停で、使い込みの問題を併せて協議していく場合もあります。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には、あえて訴訟を提起せずに、遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。
しかし、数回の調停期日で話し合っても決着がつかない場合は、それ以上は調停の中では扱ってもらえず、訴訟で解決するよう促されます。そのため、話し合いが紛糾しそうな場合は、始めから訴訟を選択しておいたほうがよい場合が多いでしょう。
交渉をしてみるのか、訴訟の提起を行う必要があるのか、調停内での解決を図るのかについて、相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
相続人の法的権利と請求に必要な資料
ここでは、遺産を使い込んだ相手方に対して、他の相続人がどのような法的権利に基づいて支払いを請求できるのか、請求するためにどのような資料が必要となるのかについてご説明します。
不当利得返還請求権
遺産は、遺産分割が終了するまでは相続人全員の共有となっているため、一部の相続人が独り占めする法律上の原因はありません。それにもかかわらず遺産を使い込んだ場合は、「不当利得」が生じています。
そのため、他の相続人は、遺産を使い込んだ相続人に対して、不当利得の返還を請求することができます。
不当利得返還請求訴訟で勝訴するためには、相手方が不当利得を得たことと、それにより被相続人(死後の使い込みの場合は、他の相続人)に損失が生じたことを証明できる証拠が必要です。
具体的には、まず、相続関係を証明するための戸籍謄本類と、預貯金が引き出されたことを証明するための通帳や取引履歴を入手します。
また、預貯金の引き出しが親本人の意思に基づかないことを証明するために、親の生活状況や認知症の程度を証明できる資料が有力な証拠となることも多いです。
これらのことを証明するために有益なのが、親が入院していた医療機関のカルテや医療記録、入所していた施設の介護記録等です。
これらの記録で、引き出しがなされた当時、親が外出できるような身体的状況でなかったり、判断能力がないあるいは著しく低下していることが確認できるような場合には、その時期における引き出しが親本人の意思とは無関係に引き出された可能性があることを推認させることができます。
また、親が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが親の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。
損害賠償請求権
一部の相続人が遺産を勝手に使い込む行為は、被相続人(死後の使い込みの場合は、他の相続人)の利益を侵害する違法行為に当たるため、他の相続人は不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟を提起することも可能です。
損害賠償請求訴訟で勝訴するためには、相手方が不法行為を行った事実とその内容や、それにより被相続人(または他の相続人)に損害が生じたことを証明できる証拠が必要となります。もっとも、具体的な証拠の内容は、不当利得返還請求訴訟を提起する場合と、ほぼ同様です。
不当利得返還請求と損害賠償請求は、どちらを選択しても構いませんが、時効期間に以下の違いがあることにご注意ください。
・不当利得返還請求権…損失の発生から10年、または権利を行使できると知ったときから5年のうち、どちらか早い方(2020年3月31日以前に使い込みが発生した場合は、「遺産を使い込まれたときから10年」)
・損害賠償請求権…損害および加害者を知ったときから3年、または使い込まれたときから20年
不当利得返還請求権損害賠償請求権が消滅時効にかかった後でも、損害賠償不当利得返還請求権は行使できることが多いです。相続開始から長期間が経過してから使い込みに気づいた場合は、時効期間も確認した上で、手続きの種類を選択しましょう。
対応する際の注意点
遺産を使い込んだ相手方へ対応する際に注意すべきポイントをまとめますと、以下のとおりです。
・事実を慎重に確認する
・十分な証拠を確保する
・冷静に話し合う
・時効に注意する
一部の相続人が親の預貯金を引き出していたとしても、私的に使い込んだとは限りませんので、証拠を集めながら、事実確認を慎重に行う必要があります。
使い込みが疑われる場合でも、なるべく感情的な対立に発展しないよう、冷静な話し合いを心がけましょう。
ただし、話し合いが長引くと時効完成により支払いを請求できなくなるおそれもあります。交渉がスムーズにまとまりそうにない場合は、早めに訴訟を提起した方がよいことも多いです。
トラブルを未然に防ぐための方法
遺産の使い込みを巡るトラブルは、事前に防止するに超したことはありません。
そのためには、親と同居する相手方が親の財産を管理するルールを取り決めることが考えられます。例えば、親の預貯金を引き出した際には、使い途をメモなどに記録するとともに、領収証や請求書などの資料も保管することとし、定期的に親族に報告することとする、などです。
相手方がルールを守らないおそれがある場合には、以下の制度の利用も検討してみましょう。
・成年後見制度…親が認知症になった後に裁判所が後見人を選任し、その後見人が財産を管理する制度
・任意後見制度…親が元気なうちに任意後見契約を結び、認知症になった後は任意後見人が財産を管理する制度
・家族信託制度…親が元気なうちに信託契約を結び、受託者(信託を受けた人)が財産を管理する制度
いずれも、信頼できる第三者が親の財産を管理する制度ですので、同居人による財産の使い込みを防止することに役立ちます。
財産の使い込みに関して弁護士に相談すべき理由
相手方が遺産の使い込みを認めて素直に返還に応じればよいですが、このようにスムーズに解決できるケースは少数です。トラブルが生じた場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、使い込みに関する事実調査から証拠の収集、相手方との交渉まで任せることが可能です。事実と証拠に基づき、冷静に交渉することで、早期の解決が期待できます。
訴訟が必要な場合も、複雑な手続きは弁護士に一任できますので、納得のいく結果が得られやすいでしょう。
使い込みのトラブルを解決した後の遺産分割についても、弁護士によるサポートが受けられます。
早期に弁護士へ相談すれば、事前に使い込みを防止する対策についてもアドバイスが受けられますし、成年後見人や任意後見人の選任申立ての手続きをサポートしてもらうことも可能です。
当事務所のサポート内容
堺鳳法律事務所では、遺産の使い込みトラブルをはじめとして、相続問題に関するご相談を全般的に承っております。特に、遺産の使い込みトラブルに関しては、他の弁護士が当初担当していたケースを当事務所が途中から引き継ぎ、的確に主張を重ねた結果、大幅に解決金額を増額させることができた実績も複数ございます。
当事務所では、年間100件以上の様々な相続に関するご相談に対して、ご相談者一人ひとりの目線に応じて親身に向き合ってまいりました。近年では受任事件の7割が相続案件であり、弁護士として相続問題に関する豊富な実績とノウハウを蓄積しております。
相続に関するご相談は初回60分まで無料です。土日や夜間も、ご予約いただければ相談可能です。
親と同居していた兄弟が遺産を使い込んでいるのではないかと疑われるときは、当事者だけで争わず、お気軽に当事務所へご相談ください。
当事務所の解決事例
亡くなった親の口座から勝手に多額の金銭を引き出していた相続人から財産を取り戻した事例