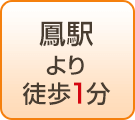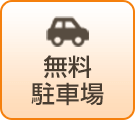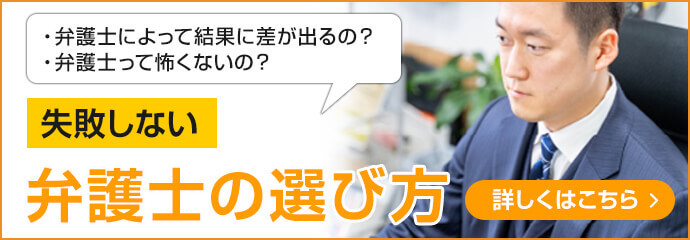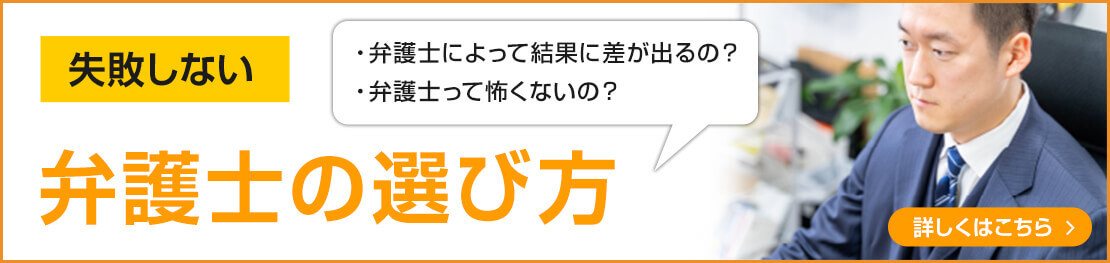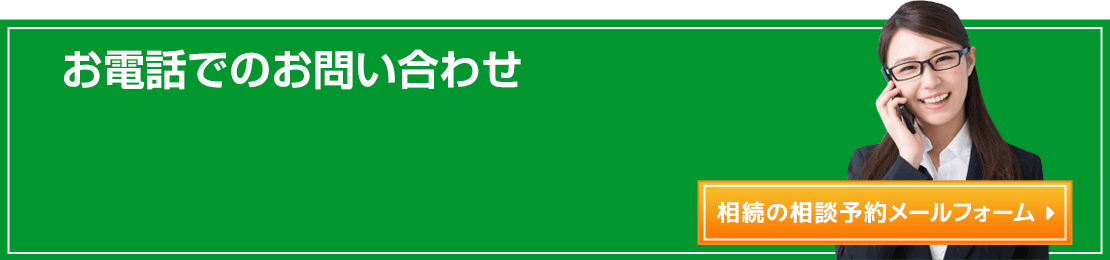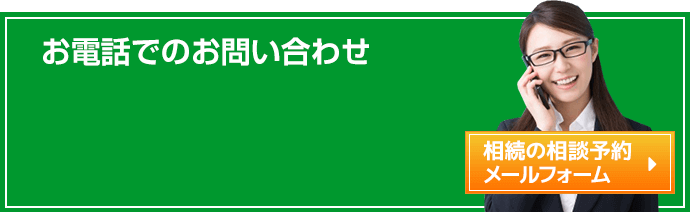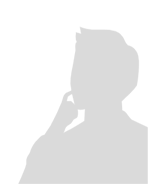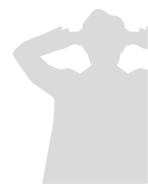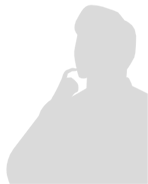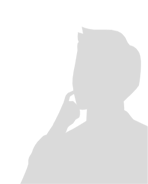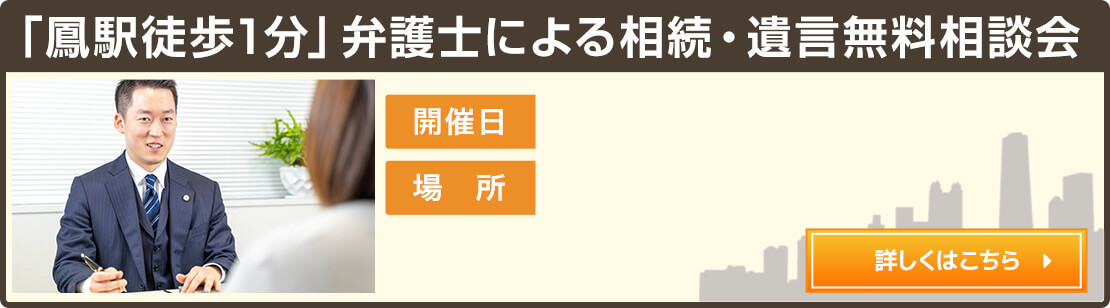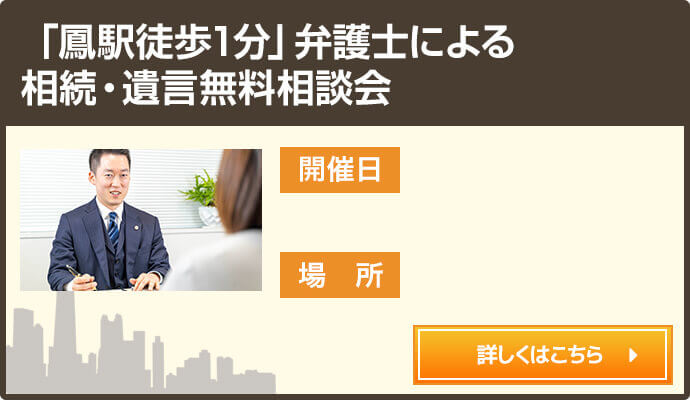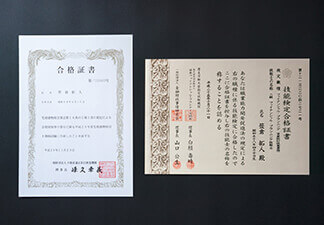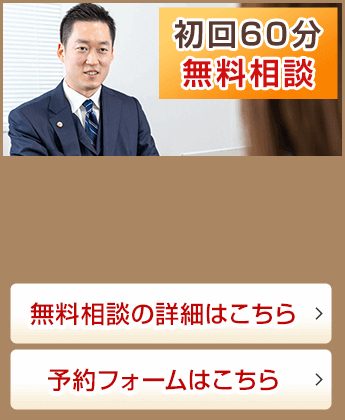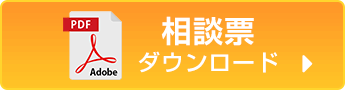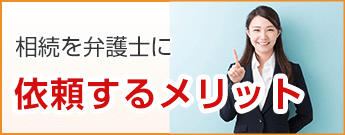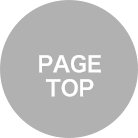遺産分割において、遺産を独り占めしようとしている相続人がいる場合の対応方法
目次
遺産分割を公平に進めようとしても、一部の相続人が遺産を独り占めしようとするケースは少なくありません。
現在の日本の法律では、一部の相続人が遺産を独り占めすることは原則として認められませんので、このような場合には相続人間での話し合い、あるいは家庭裁判所の手続きによって解決を図ることになります。
この記事では、遺産を独り占めしようとしている相続人がいる場合の遺産分割の進め方について、わかりやすく解説します。
遺産の独り占めが許されない理由
まずは、遺産の独り占めが原則として許されない理由をご説明します。
法定相続分が各相続人にあるから
各相続人の基本的な相続分は民法で定められているため、一部の相続人がそのルールを無視して遺産を独り占めすることはできません。
民法では、相続のケースごとに、誰がどのような割合で遺産を取得するのかについて、以下のとおり基本的なルールを定めています。
|
ケース |
相続分 |
|
配偶者と子が相続
|
配偶者:1/2 子:1/2 (子が複数いる場合は1/2を均等に分ける) |
|
配偶者と直系尊属が相続
|
配偶者:2/3 直系尊属:1/3 (直系尊属が複数いる場合は1/3を均等に分ける) |
|
配偶者と兄弟姉妹が相続
|
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 (兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を均等に分ける) |
このように民法で定められた相続人のことを法定相続人といい、ケースごとに定められた相続分のことを法定相続分といいます。
例えば、父が亡くなり、母と子ども3人が6,000万円の遺産を相続する場合、母は3,000万円、子どもは1人あたり1,000万円ずつの遺産を取得する権利を有することになります。
配偶者だから、あるいは長男だからといって、他の法定相続人の権利を無視することはできないのです。
遺留分が一部の相続人にあるから
被相続人(亡くなった方)が、「すべての財産を○○に相続させる」と、特定の相続人に遺産を独り占めさせる内容の遺言をしていることも多いです。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められているため、特定の相続人が確実に遺産を独り占めできるわけではありません。
遺留分とは、遺言をもってしても奪うことができない最低限の取り分のことです。具体的には、民法で以下の割合に相当する金額が遺留分として保障されています。
・直系尊属のみ相続人である場合…法定相続分の1/3
・その他の場合…法定相続分の1/2
遺言で遺留分を侵害された相続人は、侵害することとなった相続人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
例えば、前項と同じケースで亡き父が「すべての財産を妻に相続させる」との遺言をしていた場合でも、子ども3人はそれぞれ母に対して500万円(遺産6,000万円×法定相続分1/6×遺留分1/2)ずつ、支払いを請求できるのです。
母がこの請求を拒むことはできませんので、遺留分侵害額請求が行われた場合には、遺産の独り占めはできないことになります。
遺産の独り占めが許されるケース
以下のケースでは、結果として特定の相続人が遺産を独り占めすることになります。
相続人全員の同意がある
相続人全員の同意があれば、各相続人の相続割合を自由に決めることができます。特定の相続人に遺産を集中させることも、相続人全員の同意があれば可能です。
例えば、先ほどと同じケースで、母と子ども3人とで話し合った上で、「母がすべての財産を相続する」ことに全員が同意すれば、母が遺産を独り占めできることになります。
法定相続分は、相続人全員の同意が得られない場合に、各相続人が権利として主張できる相続分という意味を持つものです。
他の相続人全員が相続放棄をした
相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。
したがって、法定相続人のうち1人を除いて他の全員が相続放棄をすれば、相続放棄をしなかった人がただ1人の相続人となり、その結果、遺産を独り占めできることになります。
この方法は、相続人のうちの1人が被相続人の後継者として、事業を承継する場合によく用いられます。事業用財産や預貯金、株式などプラスの財産だけでなく、事業上の負債や未払い金などマイナスの財産も後継者に集中させるために、他の相続人が相続放棄をするのです。
遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割の進め方
遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合にも遺産を公平に分割するためには、以下のように対処していきましょう。
遺産分割協議
まずは、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、遺産の分け方を決めるための話し合いのことです。
遺産を独り占めしようとしている相続人に対して、法定相続分や遺留分など相続に関する法律上のルールを説明し、公平な相続割合で遺産を分けるように話し合いましょう。
話し合いの結果、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。その場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成しましょう。その後は、合意内容に従って実際に遺産を分けることになります。
寄与分を主張されたときの対処法
遺産を独り占めしようとする相続人が寄与分を主張することで、遺産分割協議がまとまらないこともよくあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分よりも多くの遺産を取得できる制度のことです。
例えば、特定の相続人が、被相続人が営んでいた事業を長年にわたって手伝っていた場合や、被相続人の介護や看護へ献身的に尽くしてきた場合などに、寄与分が認められる可能性があります。
日本の家族構成の実情から、配偶者や長男などに寄与分が認められ、他の相続人よりも多くの遺産を取得できるケースも多いことは否定できません。
しかし、寄与分として取得できる遺産は、あくまでも被相続人の財産の維持・増加に対して貢献した度合いに応じた分に限られます。
寄与分を主張されたときの対処法としては、その相続人の貢献度を適正に評価することが重要です。通常、遺産を独り占めする結果になるほどの貢献度が認められることはありません。
特別受益を主張されたときの対処法
遺産を独り占めしようとする相続人が、「自分以外の相続人には特別受益がある」と主張することで、遺産分割協議がまとまらないこともあります。
特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈によって受けた特別な利益のことです。
例えば、父が子どものうちの1人に対してだけ、多額の学費や事業資金、結婚資金、住宅購入資金などの援助をしていれば、父が亡くなった場合に特別受益となる可能性があります。
特別受益がある場合の遺産分割では、特別受益に相当する金額を遺産総額に加算し、その総額を法定相続分に従って分けることが基本となります。
したがって、生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた相続人の相続分は、法定相続分よりも少なくなります。
特別受益の主張をされたときの対処法としては、誰が、どれくらい、特別の利益を受けたのかを適正に評価することが重要です。
特別受益を主張することで遺産の独り占めが認められるのは、特定の相続人を除いて、他の相続人全員が法定相続分以上の特別受益を受けていた場合に限られます。このようなケースは、あまりないといえます。
なお、寄与分が認められる相続人には、同時に特別受益も認められることが多いことにもご注意ください。双方を考慮した結果、法定相続分どおりに遺産を分けることが公平となるケースも多いものです。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
調停とは、家庭裁判所において調停委員を介して相続人が話し合い、合意による解決を目指す手続きのことです。調停委員が専門的な見地に立って話し合いを仲介することにより、当事者だけで話し合う場合よりも合意に至る可能性が高まります。
調停委員は、あくまでも中立・公平な立場で話し合いを仲介しますので、調停を有利に進めるためには、法的に筋の通った主張をすることが重要です。
話し合いの手続きなので証拠の提出は必須ではありませんが、有力な証拠を提出することで説得力が増しますので、事前に証拠を収集しておくことも重要となります。
調停で話し合った結果、相続人全員が合意に至れば、調停が成立します。その場合は調停調書が作成されますので、そこに記載された合意内容に従って、実際に遺産を分けることになります。
遺産分割審判
遺産分割調停が成立しなかった場合は、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。
審判では、家庭裁判所が遺産分割の方法や内容を定めます。その際には、各相続人が提出した主張や証拠の内容が総合的に考慮されます。
調停の席上で話した内容は記録として残されていませんので、審判に移行したら、主張をまとめて記載した書面を提出するとともに、未提出の有力な証拠があれば追加で提出することが重要です。
審判の結果は審判書に記載され、各相続人へ郵送されます。審判の内容に納得できない場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告の申し立てができます。
即時抗告の申し立てがないまま2週間が経過すれば審判が確定しますので、審判書に記載された内容に従って、実際に遺産を分けることになります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
遺産を独り占めしようとする相続人がいて困ったときは、弁護士のサポートを受けることが有効です。
弁護士に相談するだけでも、ご自身のケースにおいて遺産の独り占めが認められるかどうかや、公平な相続割合などについて、正しいアドバイスが受けられます。
遺産分割を弁護士に依頼した場合には、対立する相続人との交渉を弁護士が代行してくれます。弁護士が相手方に対して相続に関する法律上のルールを正しく説明し、必要に応じて説得を図ってくれます。そのため、話し合いによる速やかな解決も期待できます。
遺産分割調停や審判が必要となった場合には、弁護士が証拠収集からサポートしてくれますし、家庭裁判所での複雑な手続きは全面的に弁護士に任せることが可能です。
弁護士という心強い味方を付けることにより、納得のいく形で遺産を分けることが可能となるでしょう。
ただ、どんな弁護士でもよいということではありません。ご自身のご意向を踏まえて、適正に対応してくれる弁護士に依頼することが肝要です。
当事務所の特徴とサポート内容
大阪府堺市の堺鳳法律事務所は、遺産相続の分野を積極的に手がけている弁護士事務所です。
遺産分割をはじめとする相続関するご相談には年間100件以上、対応しており、受任事件の7割は相続案件となっています。
遺産の独り占めしようとする相続人がいるケースなど、さまざまな事案を数多く解決に導いてきた実績があり、相続問題に関する深い知見と紛争解決ノウハウを蓄積しております。
当事務所にご相談いただけましたら、相談者一人ひとりの目線に応じて親身にご対応し、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
遺産分割の手続きをご依頼いただいた場合には、相手方との交渉から有力な証拠の収集、必要に応じて遺産分割調停・審判などの法的手続きも経て、解決に至るまで全面的にサポートいたします。
相続に関するご相談につきましては、初回60分を無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただけます。
遺産を独り占めしようとする相続人がいてお困りの際は、一人で抱え込まず、お早めに当事務所へご相談ください。