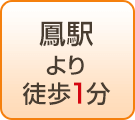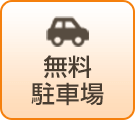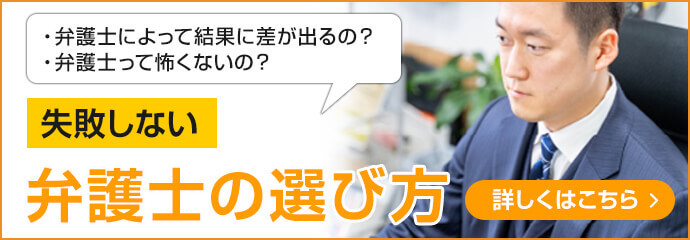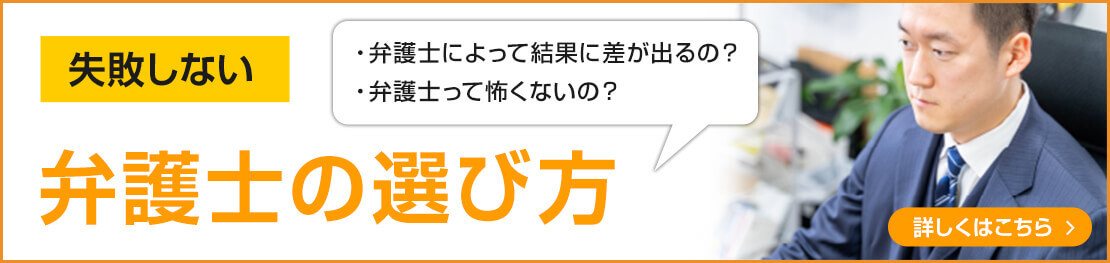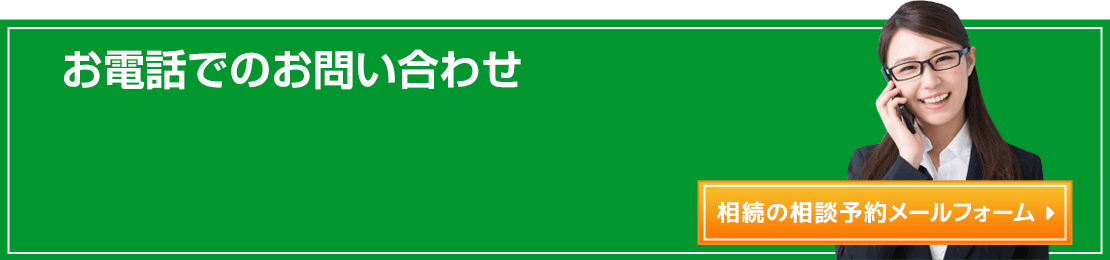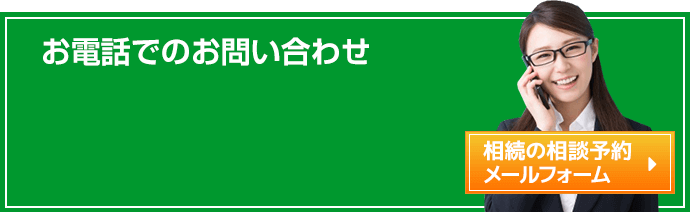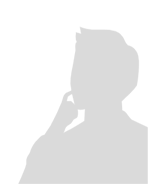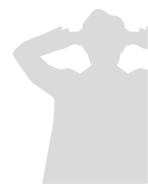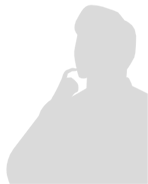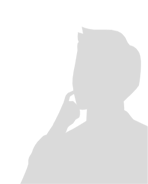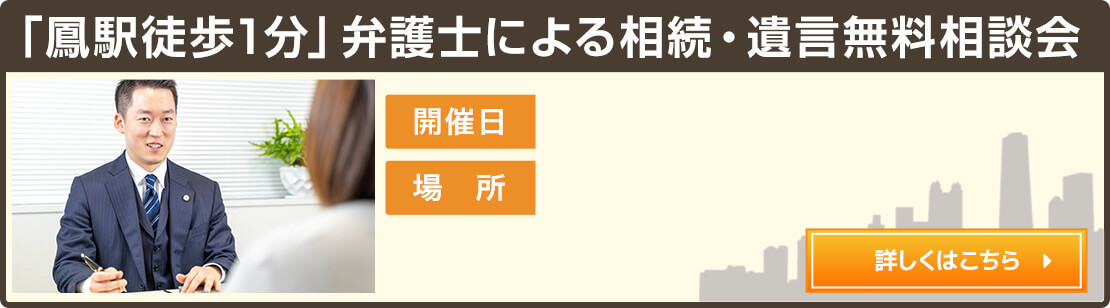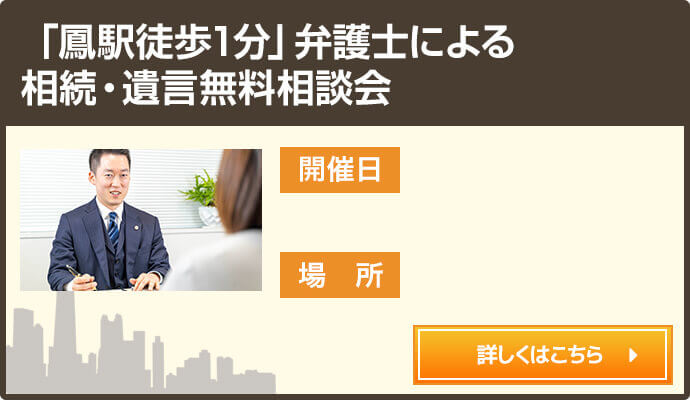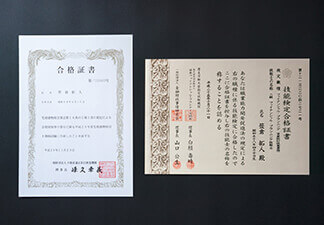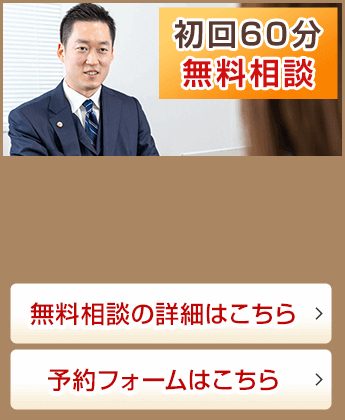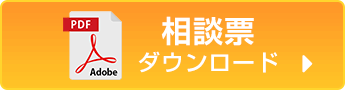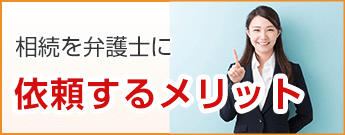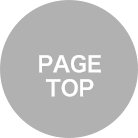被相続人に対する費用負担を主張し、約420万円の寄与分が認められた事例
- 2025.09.03

ご相談者様の属性
50歳代 男性
争点
寄与分の有無、金額
ご相談内容
ご相談者様は、お母様と自宅で同居され、お母様の介護費用など諸々の費用の負担をなさっていました。
お母様が亡くなられ、ご相談者様の兄(2人兄弟でした)から、お母様の遺産を2分の1渡すよう求められたため、お母様のために費用を負担してきたことを主張できないか、とご相談に来られました。
当事務所の対応
相手方から遺産分割調停を申し立てられていたため、調停手続きの中で、寄与分(金銭出資型)を主張していくこととしました。
それにあたって、まずは、お母様が要介護の状態であったことを証明するため、市から開示を受けた要介護認定の履歴が記載された書類を裁判所に提出しました。また、依頼者様は、お母様のために介護費用を支出した証拠(領収書など)は残しておられなかったのですが、お母様の要介護度や、介護を受けておられた内容、頻度、時間などから介護費用の推計値を割り出すとともに、お母様と相談者様の通帳を証拠として提出し、お母様には貯金がなかったことと、お母様がお亡くなりになる前後の依頼者様の毎月の支出額の変化から、相談者様がお母様のために介護費用等を支出しておられたことを裏付けました。
介護費用の推計値を算出する際には、外部のケアマネジャー(介護サービス計画作成の専門家)に意見書を作成いただきました。この意見書では、お母様が受けておられた介護の内容や客観的に明らかな介護保険の給付実績から、自己負担額を割り出していただきました。この金額と、相談者様の支出額(お母様が亡くなられる前後の支出額の差額)が概ね合致していたことから、相談者様が介護費用を負担しておられたであろうことを裏付けることができました。
その結果
当方の主張の大部分が認められ、約420万円の寄与分が認められました。それにより、法定相続分にプラスして、寄与分を加えた金額を受け取ることができました。
弁護士所感
寄与分の主張は、寄与をした証拠が存在しないことが多く、認められないことも多いのが実情です。それでも、集められる限りの証拠を集め、1つ1つ丁寧に意味付けをして主張していくことで、説得力が生まれ、寄与分を立証できたり、裁判所や相手方を説得できたりすることがあります。
どのような証拠を集め、どのように意味付けをしていくかは、弁護士が得意とするところであり、一般の方では難しいことも多いのではないかと思います。寄与分を主張することをご検討でしたら、ぜひお気軽に弊所弁護士にご相談いただければと思います。